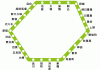おせち料理の意味 ぶり編
おせち料理の意味 第3弾ということで、今回は鰤(ぶり)の意味について解説していきたいと思います。
おせちに入っているぶりは照り焼きですが、意外と外人さんには焼き魚好きという方が多くて、以前に京都を案内したサワラ(鰆)の西京焼きを気に入って下さる方がいらっしゃいました。
鰤(ぶり)は出世魚
ブリが出世魚ってことは聞いたことがあるという方は多いと思いますが、どのように出世していくのか紹介していきますね。
ブリは一般的にはサイズが小さい順にこのような名前となっています。
- ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ
地方によっては呼び方が違うそうなので、表にもしてみましたので合わせてみてください。
(左側から右側に出世していく)
| 代表的な呼び方 | ワカシ | イナダ | ワラサ | ブリ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | ワカシ | イナダ | ワラサ | ブリ | ||
| 関西 | ツバス | ハマチ | メジロ | ブリ | ||
| 東北 | ツベ | イナダ | アオ | ブリ | ||
| 北陸 | ツバエリ | コズクラ | フクラギ | アオブリ | ハナジロ | ブリ |
| 山陽・四国 | ヤズ | ハマチ | ブリ | |||
| 山陰 | ショウジゴ | ワカナ | メジロ | ハマチ | ブリ | |
| 九州 | ワカナゴ | ヤズ | ハマチ | メジロ | ブリ | オオウオ |
出世魚って?
出世魚の代表例として、名前がよくあげられるブリですが、他にも出世魚と呼ばれる魚はいくつかあり、スズキやボラ、マイワシなども出世魚と呼ばれています。
どうして名前が変わっていくの?
同じ魚なのに名前が変わっていくということにどうして?という疑問を持ってしまう人も多いですよね。
名前が変わっていく理由としてはいくつかあるのですが、生息域や生態の変化というのがあります。
ブリも季節によって生息海域を変える魚で春から夏には沿岸、初冬から春には沖合いでその姿を見ることが出来るそうです。

By: kobakou
おせちに入っている理由
出世魚はめでたい魚として、おせちに入っているといわれています。
めでたい魚といわれている理由としては、江戸時代などに武士が元服や出世にしたがい名前を変えていくというのと同じである事から、きているそうです。
例としては、江戸幕府を開いた徳川家康も幼名は竹千代でしたが、元服後に松平元信、次に松平元康→松平家康→徳川家康と名前を変えていっています。
他にも毘沙門天で有名な上杉謙信も幼名は虎千代、元服後に長尾景虎とし、関東管領であった上杉憲政の養子となり、上杉景虎と改名。
その後に上杉憲政より1字拝借し、上杉政虎とし。今度は将軍足利義輝より1字拝借し、上杉輝虎となりました。
そして、最後に出家をし上杉謙信と名乗っています。